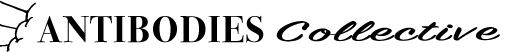ART SCRUM x ANTIBODIES Creation WS vo.2
『ART SCRUM Creation 5 days Workshop @西部講堂 』
ーANTIBOと一緒に舞台芸術作品を作ってみよう!ー
5 days Creation WS
≪コレクティブメンバー(WS参加者)募集!≫
創作活動の中で、アーティストたちは何を考え、どのように舞台作品を作るのか!?京都大学 西部講堂で、パフォーミングアーツ・舞台芸術のクリエイションWS開催です。多ジャンルのアーティストが集い、それぞれが試行錯誤し、作品が出来上がる現場に、あなたも参加し、作品制作の時間を共に過ごしてみませんか?
アーティストの方はもちろん、創作活動に煮詰まってしまってる方、何か始めたいけどどうしていいかわからない方、自分の可能性をもう少し広げたい方、いつも観てばかりだけど一回参加してみたというっていう方、イメージだけでまだ実践できていなかった方などなど、みんなで共に新しい創造的体験しませんか?
最終日には、西部講堂全体を使って「Work-in-Progress パフォーマンス」のショーイングを行います!
ぜひご参加ください!!!!!
⭐️ART SCRUM Creation Workshop Vo.2 日程
5/21 (Wed.)-25(Sun.)
5/21(wed)-23(fri) 18:00-21:00
5/24(sat) 13:00-21:00
5/25(sun) 11:00-20:00 (18:30~showing)
☆参加できない日時などはご応募時にご相談ください。
🔸ナビゲーター🔸
総合演出:ANTIBODIES Collective
振付・出演:東野祥子
音楽監修・演奏:カジワラトシオ
音楽・楽器制作・演奏:関口大和
Stage美術:アンチボ美術チーム MORIKEN 他
🔸アシスタント🔸
振付・出演:ケンジルビエン・松木萌・加藤律・菊池航・新井海緒 他
音楽:Maryln Anasonic 他
ANTIBO制作:滝村陽子
ANTIBO広報・
制作補佐:高橋理恵
申込:申し込みフォームはこちら
会場:京都大学 西部講堂 (京都市左京区吉田泉殿町)
対象:15歳以上経験不問
参加費:一般 5,000円
学生 3,000円
通しで参加通しでの参加限定となります。
問い合わせ(Art scrum 実行委員会):artscruminseibu@gmail.com
主催:Art Scrum実行委員会
協力:西部講堂連絡協議会・ANTIBODIES Collective
宣伝美術:小沼智佳
照明統括:戸邊桃花
一般社団法人ANTIBODIES Collective へのお問い合わせ (制作:滝村)
☏:080-4821-6545
✉:contact@antibo.org
What's ART SCRUM??
西部講堂連絡協議会を母体とした、様々な芸術、文学、理学専攻の大学生を中心に立ち上がった会。学生たちが自身の問題意識に近いアーティストを主体的に招き、WSを企画・運営する。
運営立案する実行委員を募集中。
ーART SCRUM代表 森本柾史氏よりvo.1を終えてのコメントーー
今回、学生企画団体「Art Scrum」を立ち上げ、実行委員として、ANTIBODIES Collectiveさんをお招きし、vol.1:プレワークショップ(以下WS)を4月5日・6日の二日間にわたり開催させていただきました。
本プレWSは、5月21日〜25日に予定されている「5days creation WS」に向けて、企画側としての感触をつかむことを目的に実施されたものです。同時に、Art Scrumにとっては記念すべき初の企画でもありました。
Art Scrumの活動目的は、「自身の創作における問題意識を解決するヒントを提示できそうなプロフェッショナルの方を学内に招き、それを多くの人と共有すること」です。
antibodies collectiveさんをお招きした理由については、当初は明確に言語化できていませんでした。しかし、振り返ってみると、私自身が学生劇団出身であり、学生劇団に所属していた頃から抱えていたいくつかの問題意識が関係していたことに気づき始めました。
たとえば、集団の中での効率的な役割分担に固執すること、また演劇の枠内にとどまった方法論から抜け出せず、「演劇」から「総合芸術」へと移行することに困難を感じていたことなどです。
このような悩みを抱えたのは私一人ではないかもしれません。演劇を続けながらも、似たような問題意識を抱いている学生が他にもいるのではないかと考えました。そんなとき、antibodies collectiveの東野さんに相談してみたところ、快く引き受けてくださいました。この場を借りて、改めてantibodies collectiveの皆さまに心より感謝申し上げます。
【プレWSを終えて】
二日間を間近で見守り、参加させていただいて率直に感じたのは、「これまで見たことのないレベルでの〈密度〉を持ったWSだった」ということです。
以下、その〈密度〉という言葉を軸に、拙いながらレポートをまとめていきます。客観的な記録として報告するべきか、主観を交えるべきか悩みつつ、曖昧なまま書き進めてしまっていることをご了承ください。
<密度>の背景にあるもの
この〈密度〉を実現させていた大きな要因は、西部講堂という空間の持つ力、そしてその空間を熟知しているナビゲーターの方々の存在にあると感じました。
「空間・時間・身体の捉え方」をテーマにしたWSの冒頭で、ナビゲーターの東野さんは「まず身体を動かしながら、この空間を感じてみてください」と話されました。参加者は、西部講堂の持つ独特な空間を意識しながら、最初は石舞台の上のみを使い、antibodies collectiveの身体の基礎動作を学んでいきました。
まず個人の身体のイメージを膨らませ、次にウォーキングをしながら近くの人とハイタッチし、そのまま二人組でワークを行い、相手の身体に対峙する中で自身の身体についてもイメージを深めていきます。活動の場は次第に広がり、木の斜面、コンクリート床、青い壁に囲まれた景色の中で音楽が流れると、テーマに沿って15m×30mほど(おそらく)の西部講堂全体が、各参加者の表現で満たされていきました。
一見するとささやかなステップの一つひとつが、「この空間の中でいかに動くか」という課題を、参加者の中に無意識あるいは意識的に生み出していたように思います。
ここで特筆すべきなのは、ワークが終了するたびにペアでフィードバックを行い、次のワークでは新たなペアと組むというサイクルを、体感で2〜5分という短い時間で繰り返し行った点です。
これは個人的な話になりますが、中学時代の柔道部で行っていた「乱取り(実戦形式の練習)」を思い出しました。3分間のタイマーを鳴らし続けながら、短い休憩を挟みつつ次々に相手を変えて実戦を行う、非常にスピーディでアグレッシブな方法です。他者と技術を共有し、自身の技術を試すという意味では、まさにこのWSにも共通していたと感じます。
この〈密度〉を支えるフィードバックの時間について、「普段から創作に取り組んでいる人でなければ成立しないのでは」と思われるかもしれません。しかし、実際には「自分のやりたいこと」と「今、自分が感じていること」を他者から聞き入れる姿勢さえあれば、誰にでも可能なのだと体感できたWSでもありました。
また、「参加者同士で自分の成果を共有する」スタイルは、他のWSである「舞台空間づくりWS」「不思議な音の実験室」においても共通して見られました。
【舞台空間づくりWS】
このWSでは、実際に丸太を用いて組んだ巨大な立体構造物が登場しました。その印象は「構造物」というより「幾何学的な立体物」と呼ぶほうがしっくりきます。
この言葉の違いは、何かを立てる際に「土台に対して垂直で重厚なイメージ」があるかどうかに関わるのではないかと考えました。そして、この差異は、antibodies collectiveのパフォーマンスにおいて重要な要素であるとも感じました。
ダンサーの東野さんが丸太の上に登り、普段どのような動きをしているかを紹介してくださると、その一瞬の光景だけでも非常に圧巻でした。そして、身体の周りに張り巡らされた丸太という構図は、それだけでも強い想像力をかき立てるものでした。
この「ダンサーが丸太の上に登り、丸太の隙間でパフォーマンスが可能である」という、とても単純な事実を体感できたことは、後に行われた美術プラン作成において非常に重要だったと思います。
参加者には西部講堂の図面と、竹櫛、針金が配られ、それぞれが「自分ならどう組むか」を模型で考える時間となりました。比較として適切ではないかもしれませんが、以前参加した演劇の美術WSでは、まず舞台用語の説明から始まり、経験者と初心者の情報差を埋めるために多くの時間と労力を割く印象がありました。
しかし今回は、模型を実際に組みながら「どうすれば倒れないか」「どんな形にしたいか」を体験的に考えることができました。約1時間半の制作時間中、参加者たちは驚くほどの集中力を保っていました。
「これが実寸大の丸太だったら?」「この間をダンサーが歩いたら?」と想像し出すと、思考が止まらなくなるような時間でした。最後には、全員が自分の作った模型について、コンセプトや想定される上演方法などを共有しました。配置の規則性を重視した模型、ダンサーの動きをイメージしたもの、曲面を描き出そうとしたものなど、まさに十人十色の舞台美術案が並びました。
【不思議な音の実験室】
私が個人的に最も好きだったWSが、この「不思議な音の実験室」です。ナビゲーターのカジワラさんはWS経験も豊富な方で、ぜひどこかの機会でご本人から直接話を聞いてほしいと思います。ここでは、簡単に概要を記します。
WSはまず、「音とは何か」という問いから始まりました。学校教育の中で生まれてしまった「音楽」に対する誤解——つまり、「音楽」という名詞的な捉え方を、「音楽をする」という動詞に変えたいという強い信念が語られました。
「技術や知識に縛られない、自分だけの自由な音楽を奏でる可能性」について語られた後、なんと2時間半の間で、実際に参加者自身が録音し、自分たちだけの音楽を作り上げるというところまで体験できたのです。これはまさに、カジワラさんが冒頭で話していたことを体現した瞬間でした。
antibodies collectiveによる録音のデモンストレーションの後、参加者はグループに分かれ、西部講堂にある音を探しに出かけました。扉の音、木の床の足音、外の枯れ葉が擦れる音、外国人の声、課外棟の機械音——それぞれが見つけた音を、距離感も含めて丁寧に録音していきました。
一見すると散らばったように思える音たちも、連なりを持つことで一つのドラマが立ち上がっていく様は、非常に興味深く、なぜこの短時間でそれが可能だったのか、不思議に感じるほどでした。まるで魔法のようでした。
けれども、それは偶然ではなく、冒頭に語られていた「音とは身体に密接した概念である」という視点が鍵になっていたのだと思います。私たちは手を叩く、洗い物をする、椅子に座る、外を歩く——そんな日常の行動の中で、すでに様々な「音楽をして」おり、そこに何かを無意識に感じ取っているのです。
そのことに気づいたとき、WSが終わった帰り道から、自分の見えている世界が少しだけ変わっているように感じられました。とても素敵なWSでした。 ART SCRUM代表 森本柾史